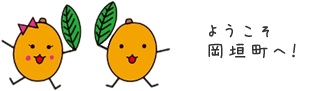令和7年度岡垣町一般会計予算のご審議をお願いするにあたり、私のまちづくりに対する基本姿勢と予算の概要を申し上げ、議員ならびに住民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。
令和7年度 岡垣町長施政方針
はじめに
はじめに、令和6年度を振り返りますと、10月には「マイナビ ツール・ド・九州2024福岡ステージ」が宗像市と岡垣町を舞台に開催されました。町内外から多くの方にご来場いただき、大きな事故もなく無事に大会を成功させることができました。これもひとえに、住民や事業者の皆様のご理解とご協力のおかげであり、改めて心より感謝を申し上げます。
また、国政においては、10月に石破内閣が発足しました。日本の活力を取り戻す経済政策である「地方創生2.0」を起動し、都市も地方も、安心・安全で心豊かに暮らせる持続可能な地域経済社会を作るため、新たに地方公共団体が自由度の高い事業を行うことができる交付金を創設し、地方の取り組みを後押しすることとされています。今後も国の動向を的確に把握し、機動的かつ弾力的に対応していきます。
12月には民間企業による「街の幸福度ランキング&住み続けたい街ランキング」が発表され、3年連続で高評価をいただきました。また、「子育て環境が充実している自治体ランキング」でも福岡県内で第1位に選ばれるなど、住民の皆様とともに進めてきたまちづくりに対する一つの評価ではないかと受け止めています。これからも安心・安全な暮らしを守り、自然と共生し、岡垣らしい幸せを感じてもらえる、住み続けたいと思っていただけるようなまちづくりを進めていきます。
まちづくりの基本姿勢
次に、私のまちづくりの基本姿勢について申し上げます。
2期目となる町政運営も、社会情勢などの変化に適切に対応しながら、数十年先の岡垣町を見据えて今やらなければならないこと、そして、今暮らしている住民の皆様の幸福度を高める取り組みを同時に進めることで、第6次総合計画に掲げる目指すまちの将来像「自然と共生する しあわせ実感都市 岡垣」の実現に向けたまちづくりを継続して進めてまいります。
それでは、令和7年度のまちづくりの諸施策について申し上げます。
本年は甚大な被害が発生した阪神・淡路大震災から30年の節目の年となります。大震災以降も日本各地で大規模な自然災害が発生しており、昨年元日に地震に見舞われた能登半島では、9月の記録的な大雨により、復旧途上にあった被災地において、再度、甚大な被害が発生しました。こうした複合災害は、今後、発生頻度が高まっていくことが懸念されており、ハード・ソフト一体となった総合的な防災対策の推進が必要となっています。また、高度成長期以降に集中的に整備された橋梁、道路、上下水道などのインフラの老朽化も顕在化しており、大きな社会課題となっています。
このような状況を受け、国においては、国土強靱化の取り組みの更なる加速化・深化を図るため、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」を策定し、重点的かつ集中的に取り組んでおり、令和7年度は取り組みの最終年となっています。また、東日本大震災を教訓として、防災・減災対策を早急に進めることができるよう創設された「緊急防災・減災事業債」も令和7年度までの時限措置とされており、これらの対策などを活用して指定避難所や指定緊急避難場所となる公共施設の整備を行います。現在、令和8年度からの国土強靱化実施中期計画の策定が行われており、埼玉県八潮市での大規模な道路陥没事故を受けて、インフラ全体の老朽化対策の検討も進められることから、国の動向を注視し、引き続き、防災・減災の取り組みを進めていきます。
それでは、具体的な取り組みとして、まず、施設整備について述べます。令和7年度当初予算に計上する予定としていた町内小中学校屋内運動場の空調設備の導入や吉木小学校特別教室棟改修を、国の補正予算による補助金などを最大限活用するため、前倒しして実施することとしており、空調設備の導入は2か年にわたって予算を計上しています。令和7年度当初予算では、総合グラウンドの照明のLED化や総合グラウンド、町民体育館のトイレ改修、個別施設計画に基づき施設の長寿命化を図るために実施するサンリーアイ施設や役場庁舎トイレの改修、山田小学校外壁・屋上防水改修などを実施することとしています。これらの投資的経費の増加により、令和7年度の町債の発行予定額は前年度を大幅に上回る見込みですが、災害に強いまちづくりの推進やインフラの充実と適切な維持更新を進めるため、積極的な予算編成を行いました。
次に、交通インフラについてです。昨年2月に国道3号岡垣バイパスが4車線化・フルランプ化となりました。現在、県道原・海老津線バイパスと県道岡垣・宗像線バイパスの整備が進んでおり、本町の道路交通網の形成が図られています。そして、鉄道もJR九州の3月15日のダイヤ改正により全ての快速列車が海老津駅に停車することで利便性の向上が図られます。一方で、本年10月から西鉄バス松ヶ台循環線が廃止となります。交通インフラは住民生活やまちづくりに欠かせない重要なものであるため、当該路線をコミュニティバスによる運行とし、維持してまいります。
また、インフラの充実とともに重要なのが安全対策です。昨年、小中学校児童生徒が被害者となる交通事故が発生しており、交通安全対策の重要性を改めて痛感したところです。交通安全施設は、これまでも通学路安全確保の取り組みとして、教育部局や道路管理者、警察、PTAなどが連携して合同点検などを実施し、老朽化した施設の更新や新たな整備を行ってきました。令和7年度においても国の補助金を活用しながら要望などに基づく必要な工事の予算を計上しています。また、かねてより小中学校児童生徒の保護者や地域住民が設置を求めている国道3号岡垣バイパス東交差点の横断歩道橋については、現在、議会の協力もいただきながら国に対して、要望を行っているところです。今後も日頃からの点検や小中学校、PTA、自治区からの要望などを基に、交通安全対策の強化を図っていきます。
そして、本町の水道事業などにおける安全対策の一つにPFOS・PFOAへの対応があります。芦屋基地に近接する糠塚水源井戸において、PFOS・PFOAが検出されています。今後も水道水の安全確保の徹底を図るとともに、芦屋基地や九州防衛局に原因究明などを求める要望活動を行うなど、引き続き、適切かつ迅速に対応していきます。また、透明性を確保しながら、適宜適切な情報発信に努め、住民生活への影響や不安の解消を図る取り組みとして、井戸の水質検査の補助を行うこととしています。
そして、忘れてはならないのが平和を願う継続した取り組みです。世界に目を向けると、ウクライナやガザ地区では今も戦火が続いています。我が国においては、本年は戦後80年の節目の年にあたります。本町では未来を担う子どもたちに核兵器と戦争の悲惨さを伝え、命の尊さや平和について考える機会として継続して平和事業を実施してきました。本事業では3年ごとにサンリーアイでイベントを開催しており、令和7年度はこの年にあたります。このイベントを通じて多くの住民の皆様が平和について考える機会を提供したいと考えています。
私は、これまでもこれからのまちづくりを進めていくうえで、まずは日本の人口が減少していくことをしっかりと認識しておく必要があるということを申し上げてきました。令和5年12月に国立社会保障・人口問題研究所から「日本の地域別将来推計人口」が公表され、我が国の人口は2050年には1億400万人余りになるとされ、本町の人口は2020年と比較すると約18%減少して2万5千人余りになると推計されました。また、北九州市と近接する17市町で構成する北九州都市圏域全体では、2020年と比較すると約24%の人口が減少すると推計されています。
令和7年度は、住民アンケート調査などを実施し、第6次総合計画の中間評価を行うこととしており、人口減少への対応とあわせて、中間評価の結果も踏まえたまちづくりを進めてまいります。
そのうえで、数十年先の岡垣町を見据えて今やらなければならない取り組みとしては、JR海老津駅の周辺整備や学校施設の適正配置の検討、第2期に向けた公共施設等総合管理計画の改訂作業を進めます。また、この取り組みの一つとして昨年誘致した屋内スイミング施設が本年5月に開設予定となっています。天候に左右されず安定的で専門性の高い小中学校の授業実施のほか、教職員の負担軽減や財政面でも効果があると考えています。
令和7年度のまちづくり
令和7年度一般会計当初予算は、対前年比7億5百万円増の129億9千8百万円であり、過去最大の予算規模となりました。
第6次総合計画の基本目標に沿った新たな施策や重点的に取り組む施策は次のとおりです。
(1)自然を守り、活かし交流を生むまち
まず、「自然を守り、活かし交流を生むまち」です。
三里松原や美しい海岸などの自然を守るため、官民が連携した環境保全活動を引き続き推進するとともに、水辺の環境学習の実施や環境問題講演会の開催などにより、環境を守る意識の啓発に努めます。
三里松原の保全については、三里松原防風保安林保全対策協議会の保全活動を支援するとともに、松林が直接住民の目に触れるように可視化を進めている西側地域において広葉樹などの伐採を行い、アダプト制度への参加団体の活動範囲の拡大を図ります。また、森林保全については、森林環境譲与税や県からの交付金を活用した間伐などによる森林再生の取り組みに加えて、県と連携して放置竹林対策を推進します。
ごみの減量化・再資源化については、ごみ処理経費や温室効果ガス排出量の削減につながることから、引き続き、意識啓発や情報提供、資源回収活動への補助などを行い、住民・事業者・行政が一体となった取り組みを進めていきます。
住民の生活にとって欠くことのできない貴重な資源である地下水については、地下水採取量の制限などを行うため、本定例会に条例改正の議案を提出しているところです。今後も住民が良質な地下水を将来にわたって享受できるように取り組みます。
(2)地域資源を活かし発展するまち
次に「地域資源を活かし発展するまち」です。
農業振興については、農業生産の基盤となるため池や農業用水路などを改修し、農業生産力の向上や農作業の効率化、施設管理の省力化を図ります。また、本町の地域農業の諸課題に対応するため、これまで進めてきた各個別施策のほか、新たに将来を見据えた本町独自の農業施策を展開することで、継続した農業経営の発展や地域農業の振興に繋がる農業者支援を推進します。
漁業振興については、藻場再生や有害生物駆除活動への支援を充実させることで、漁場機能の回復や漁獲量の増加に向けた取り組みを進めます。
商工業振興については、商工会と連携を図りながら、制度融資などによる経営支援、新規創業支援などに継続して取り組むとともに、電子クーポンの給付やプレミアム商品券の発行補助などにより町内での消費循環を促進します。また、中小企業の人手不足が深刻な問題となっているため、新たに岡垣町商工会が遠賀町商工会と連携して行う合同企業説明会に対して支援を行います。
観光振興については、「ツール・ド・九州2024」の開催地である強みを活かし、新たなサイクルイベントの開催などを通じて、サイクルツーリズムをさらに推進し、自転車の聖地と言われるように認知度向上を図ります。また、魅力ある観光地づくりには民間の力が欠かせないため、観光協会との連携を一層強化し、官民一体となって観光振興に取り組みます。
(3)人・つながりが育つまち
次に「人・つながりが育つまち」です。
子育て支援については、特に重点を置き「子ども医療費の自己負担額の見直し」や「中学校の給食費の半額補助」などライフステージに応じた切れ目ない支援を充実させ、子育て支援策を体系的に整理した「おかがき子育て応援パッケージ」などにより周知を図ってきました。また、待機児童の解消のため支援を行ってきた認可保育所が、本年4月に開所を予定しています。昨年4月1日の待機児童数は25人となっていましたが、受入体制の拡充により大幅に減少する見込みです。そして、利用児童数の増加に対応するため、本年4月に海老津第三学童保育所を開設することとしています。
今後は、本年3月に策定する「こども計画」に基づき、子どもにとっての最善の利益を考えながら、子ども施策や子育て支援の更なる充実に向けて、引き続き取り組んでいきます。
また、学校教育においては、令和2年度から3年度にかけて整備した児童生徒のタブレット端末の更新や不登校支援のための学校適応指導教室の拡充などにより、教育内容の充実と学習機会の確保、ICTの推進を図ります。
学校施設適正配置の検討については、本年2月の学校適正配置検討審議会からの答申や議会からのご意見も踏まえ、町の基本方針を定めたうえで、方針に沿って岡垣中学校の施設整備を計画的に進めていきます。また、小学校施設においては、老朽化により施設面での対応の検討が必要になっていることから、小規模校のあり方を含めた学校施設の適正配置など具体的な検討を進めます。
学校給食については、食材費の高騰による保護者の負担を増やすことなく栄養バランスのとれた給食を提供するため、 公費負担を拡充します。また、本定例会に条例制定の議案を提出している学校給食の公会計化に取り組み、安定的な給食を提供します。
(4)誰もが元気で自分らしく暮らせるまち
次に「誰もが元気で自分らしく暮らせるまち」です。
本年3月に策定する「第3次健康増進計画」に基づき、生涯にわたって健康で自立した生活が送れるように健康に対する意識や健診受診率の向上を図り、生活習慣病の発症や重症化を予防します。また、予防接種法に基づく定期予防接種を実施し、令和7年度から新たに高齢者の帯状疱疹の発症や重症化を予防するため、ワクチンの定期接種を開始します。
地域住民が抱える課題が複雑化・複合化する中、「福祉総合計画」に基づき、地域共生社会の実現に向けた取り組みを進めます。また、既存の相談支援や地域づくり支援の取り組みを活かし、分野別の支援体制では対応が困難な複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、重層的支援体制整備事業の充実に取り組みます。
高齢者福祉では、介護予防・日常生活支援総合事業や認知症施策などを推進し、新たに屋内スイミング施設を活用した「水中楽らく運動教室」の開催、介護予防サポーターなどの地域の担い手の活動支援の充実や「認知症カフェ」への支援の拡充を図るなど、高齢者が安心して暮らせる地域づくりを推進します。また、シニアカーの利用に関する周知や購入費用を補助することで、運転免許証を返納した方や筋力が低下した方などの移動手段の確保や外出機会の拡大につながるように取り組んでいきます。
(5)安全・快適に暮らせる持続可能なまち
次に「安全・快適に暮らせる持続可能なまち」です。
冒頭で述べたとおり、令和7年度は「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」などの最終年度であり、これらの対策などを活用して、公共施設などの適切な維持更新に力を入れて取り組みます。町道や橋梁においても補修や更新を進め、安全性や快適性の確保を図っていきます。
JR海老津駅の周辺整備については、事業用地の取得を進めているところです。今後も民間活力を活かした「まちなか居住の推進」と「交通結節機能の強化」に向け、地権者などへの十分な説明を行いながら、引き続き、事業の推進に取り組みます。
そして、自治区の自主防災組織の活動の活性化に向け、危機管理専門員による出前講座や防災訓練の運営支援などを実施し、地域における防災力の強化を推進します。
計画推進の基盤
次に、まちの将来像の実現を図るための「計画推進の基盤」についてです。
まず、地域コミュニティ活動についてです。
自治区については、令和4年度に実施した自治区懇談会で把握した課題などを踏まえて、令和6年度から広報紙の配布方法を事業者によるポスティングに変更するなどの大規模な負担軽減策に取り組んできました。今後も、自治区懇談会で出された課題の解決に取り組むとともに、自治区長会と連携しながら自治区運営の支援を行います。
また、校区コミュニティについては、令和4年度、5年度に実施した校区別懇談会を受け、コミュニティ活動の推進を図るために地域づくり交付金を増額するとともに、人材の確保や育成などの取り組みをさらに進めていきます。
次に、自治体DXの推進についてです。
人口減少局面において、DXを推進し、業務の効率化による生産性の向上を進め、住民の利便性や行政サービスの維持・向上を目指すことが必要不可欠です。住民サービスの利便性を向上させるために、オンライン申請可能な手続きの拡大や、便利さを実感していただくため、コンビニエンスストアでの証明書発行手数料を一時的に減額するなど「行かない窓口」の実現に向けた取り組みを進めていきます。また、行政事務の効率化に向けて、財務会計システムの電子化をさらに進め、ペーパーレス化による適切な情報管理と迅速な事務決裁を導入します。さらに、電子入札システムを導入し、契約事務の透明性の確保や効率化、事業者の利便性の向上を図ります。
次に、広域行政の推進についてです。
人口減少や災害対応など広域的な取り組みが必要な課題が増加しており、他の自治体との連携の推進が重要であると考えています。まずは、遠賀郡4町による相互の連携体制を強くするとともに、遠賀・中間地域広域行政事務組合での事務の共同処理や北九州市を中心とした北九州都市圏域での人口減少などの共通した課題に対応するためのさまざまな事業連携により、行政運営の効率化や質的向上を図ります。
次に、組織力の強化と働き方改革の推進についてです。
近年の人口減少や少子高齢化の進展、大規模災害や感染症の発生など様々な課題や状況の変化に対応できる人材を育成するため「人材育成基本方針」の改定に取り組みます。また、職員研修計画に基づき、独自研修や派遣研修を実施し、職員の資質や能力の向上を図ります。加えて職員が業務改善や政策立案に取り組むための時間を確保するとともに、働きやすい労働環境を整えることで、業務の効率化や生産性の向上による住民満足度の高い行政サービスの提供や人材の確保と職員の働き方改革につなげます。
最後は、健全な財政運営についてです。
持続可能なまちづくりを進めるためには、健全な財政運営が欠かせないことから、行政改革推進計画の推進や事務事業のスリム化などに取り組み、近年、基金残高を増加させる一方で町債残高を縮減させ、安定した財政基盤の確立に努めてきました。今後の財政運営においても、これまでと同様に財政規律の確保に努めていくことは当然ですが、財政の健全性を保ちつつ、人口減少など数十年先の岡垣町を見据えて今やらなければならないこと、そして、今暮らしている住民の皆様の幸福度を高める取り組みをさらに推進する必要もあります。難しい舵取りですが、「財政の健全性の確保」と「事業の推進」のバランスを図り、持続可能なまちづくりを進めていかなければならないと考えています。令和7年度はまちづくりへの投資を積極的に行うこととしていますが、財政負担が過度に増大し、将来に向けた財政の健全性が損なわれるようなことがないように、将来を見据えた長期的な視点で、計画性をもって安定的な財政運営を行い、財政健全化に継続して取り組みます。
また、健全な財政運営においては、財源の確保が重要となります。このことから、おかがき応援寄附金については、引き続き魅力的な返礼品の拡充やリピーターの増加に努めます。また、新たな取り組みとして、事業者の商品開発や返礼状況に応じた支援制度を創設し、町のイメージアップ商品の創出、ひいては返礼品の充実につなげます。また、使い道を明確にして寄附金を募集する、クラウドファンディング型ふるさと納税の取り組みを拡充させます。これらの取り組みにより、更なる寄附金の受入拡大を図るとともに、本町の認知度の向上を図り、シティプロモーションの推進や地域活性化につなげていきたいと考えています。
そして、新たな財源確保による住民サービスの向上と協働のまちづくりの推進を目的に、モデル事業として、ふれあいスポーツ広場の管理についてスポンサー制度を導入します。今後は都市公園などにも対象を拡大したいと考えています。
むすび
以上が、私のまちづくりに対する基本姿勢と、令和7年度の主な事業の概要です。
繰り返しになりますが、人口減少が進む中でも持続可能なまちづくりを進めるため、令和7年度の町政運営においても、数十年先の岡垣町を見据えて今やらなければならないこと、そして、今暮らしている住民の皆様の幸福度を高める取り組みを同時に進めることで、「自然と共生する しあわせ実感都市 岡垣」の実現に向けて、全力で取り組む所存です。
議員ならびに住民の皆様のご理解とご協力を重ねてお願いいたしまして、令和7年度の施政方針とさせていただきます。